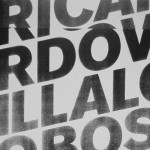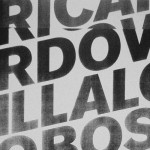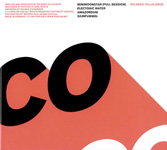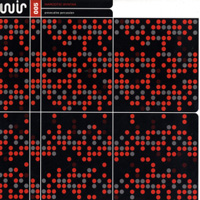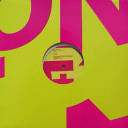タグ: perlon
RICARDO VILLALOBOS / VASCO (PERLON) CD
http://www.perlon.net/ …
RICARDO VILLALOBOS / VASCO EP PART 1 (perlon) 2LP
http://www.perlon.net/ …
LUCIANO / FOURGES ET SABRES (PERLON)12″
http://www.perlon.net/ …
NARCOTIC SYNTAX/provocative percussion(wir)2LP
http://www.narcoticsynt…
V.A./SUPERLOOOONGEVITY(PERLON)4LP
http://www.perlon.net/ …
ARK/CALIENTE(PERLON)CD
CalienteARK Amazonで詳しく見…
RICARDO VILLALOBOS / THE AU HAREM D’ARCHIMEDE (PERLON)3LP
http://www.perlon.net/ …
HORROR INC./I PLEAD GUILTY(PERLON)12″
http://www.perlon.net…
COPACABANNARK/TO BEACH OR NO TO BEACH(PERLON)12″
http://www.mad-net.de/p…
MELCHIOR PRODUCTIONS / the meaning (playhouse) 2CD
http://www.ongaku.de/ 最…
NARCOTIC SYNTAX/CALCULATED EXTRAVAGANT LICENTIOUSNESS EP(PERLON)12″
パーロンからリリースされる作品ってみんなユーモ…